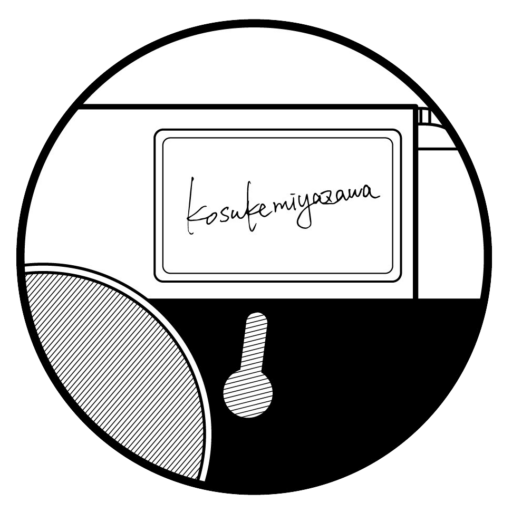撮っているようで撮らされている
撮っているようで撮らされている

この頃、写真を整理したり見返したりしていて気付いたことがある。これまで自分で撮った花の写真は、自分が名前の知っている花しか被写体にしていないということだ。チューリップにバラ、コスモス、彼岸花、ミモザ、紫陽花、桜などのごく一般的なもので尚且つ季節感がわかるような花の写真しか撮っていない。外を歩いたり旅先で出会ったものは自分としては感性の赴くままに写真を撮っているつもりだった。理由を考えていると漠然ではあるが自分なりの答えが出てきた。自分が撮っている花は、名前を知っている花や見たことのある花だけだと言うことだ。つまり、花の名前を知らないと仮に道端で咲いていても気づかないし、そこへカメラを向けることがないのだと気づいた。

いつも使わない頭を使ってふにゃふにゃと思案して一旦得た私見を辿ってみる。ここ最近、見聞きして感心したものの中にスイスの言語学者ソシュールの『一般言語学講義』がある。和訳した原著を読んだわけでも言語学を勉強したわけでもないがYouTubeやまとめサイトなどを幾つも読み漁り、思考方法として面白いな、と感じた。ソシュールはそれまで一般的であった「言語名称目録観」を否定した。言語名称目録観とは世界にはまず存在があり、そのモノに対してラベルという形で名前がついているという考え方だ。ソシュールはこれを否定した上で、世界は構成要素(モノ)が初めから存在しておりそこへ名前をつけているのではなく、モノに名前をつけることで他のモノとの対立関係を生み言葉が生まれると主張した。そのため使う言語が違えば切取り方も違うのでみている世界も違ってくるというものだ。日本語では「蛾」と「蝶」を区別するがフランス語では「Papillon(パピヨン)」と呼んで区別しないのが良い例になっていると思う。誤解を恐れずにいうと、モノがあるから名前をつけているのではなく、名前をつけるからそのモノが誕生するのだ。この考え方を知ったときは非常に感銘を受けた。





この考え方を持って改めて写真ライブラリを見ると名前の知らない花はほぼ存在せず、名前の知っている花しか撮っていない理由が少し理解できたような気がする。カメラを持って何か撮ってやるぞ!と躍起になって好きなようにシャッターを押しているような気分になっていたが全然そんなことなかったのだ。自分の持ち合わせている知識の中にある花を街中や旅先で見かけた時、脳内では「あっっ!あの花だ!知ってる!きれいだ!」となってカメラを向けていたのだ。もう少し正確にいうと季節の中で咲いている花は種類が多くあるにもかかわらず自らが持ち合わせている言葉で世界を切り分けると知らない花がノイズとして処理され、知っている花にのみ自分が興味を示していただけと気づいた。自分が知らないもの=名前がついていないモノなのだ。ソシュールに言わせれば言語が違えば世界の区切り方や切り取り方が違う。この考えを自分の状況に沿って噛み砕いてみると、そもそも同じ言葉を使ってる同じ国の人でも知っている言葉の量や認知できるモノの量で見えている世界の解像度が全く違うということだ。きれいだと思って切ったシャッターやあの時自分で撮ったと思った花の写真は実は自分の認知している解像度の低い世界に知らず知らずのうちに撮らされていたのかもしれない。